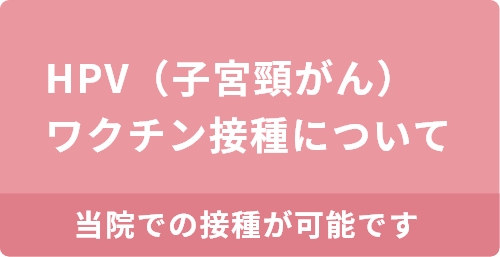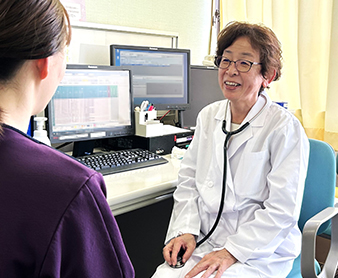外来診療のご案内
- 診療時間
-
月曜~金曜日 午前外来 09:00 〜 11:30
午後外来 13:30 〜 17:00土曜日午前外来 09:00 〜 11:30
- 外来予約
-
0470-25-5121
予約受付時間
月曜日~金曜日 08:30~17:00
土曜日 08:30~12:00
※ 休診日は日曜日・祝日・年末年始となります。
※ 一般外来は予約制となります。
救急外来について
当院では、二次救急指定病院として365日24時間体制で診療を行っております。一次救急(入院を必要としない方)、二次救急(入院・手術を必要とする方)を対象としております。
救急外来での診療を希望される方は病院へ事前に電話連絡をして下さい。
- 代表電話
-
0470-25-5111
※ 受付時間は、365日24時間